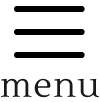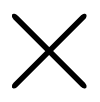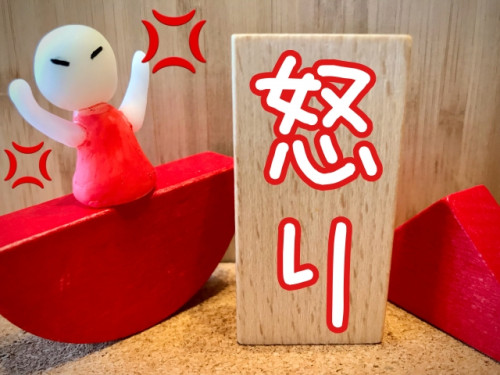ブログ
価値観や考え方の違う人との付き合いかた
20年前に比べると、SNSの発達だったり、
ITの目まぐるしい発達によって
様々な情報が簡単に手に入ります。
だからこそ、価値観や考え方の違いを
目の当たりにする機会も
多くなっています。
人間というものは、「違う」ことに
過剰に反応してしまうもの。
「違う」=「分からない」
知っている物やことには「安心感」
知らないもの、知らないことには
「恐怖感」や「不安感」を抱きます。
その恐怖感や不安感を消すために
否定や攻撃を手段として使います。
否定や攻撃をすることで
その一瞬は不安や恐怖をごまかす
ことはできるでしょう。
しかし、
その不安や恐怖はまた
価値観や考え方の違う人を前にすると
どこからともなく湧き上がってきます。
相手に否定や攻撃をしたところで
何にも変わりません。
「この人何か違うな」
「言っていることが分からない」
と感じた時には、無意識に
恐怖や不安が湧き上がっている
可能性が高いです。
その恐怖や不安の原因は、
相手ではありません。
「知らない」「分からない」
などが原因です。
なので、
相手を否定しようが、
相手を攻撃しようが、
何ひとつ解決には結びつきません。
相手を否定や攻撃したくなったら
「相手に原因がない」ことを
思い出してください。
SNSだけの問題ではありません、
日常の関わる全ての人に
言えることです。
会社、家族、友人、活動仲間。
日常の人間関係において
知らない、分からないことには、
不安や恐怖を感じるものです。
そのことを自覚して、
知らない、分からないことは
相手に質問したり、
その道に詳しい専門家に聞きましょう。
知らないことや、分からないことを
少しでも認識して(理解はしなくても)
自分の中から湧き出る
不安や恐怖を減らしましょう。
そうすることで、
争いの少ない、安心安全な関係性を
築きましょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここからはお知らせです。
「色彩メンタルトレーニング体験会」
毎月第4水曜日、土曜日に
開催しています。
詳細はチラシ画像でご確認ください。
体験会では、
色彩とコミュニケーション心理学を
融合した「心理テスト」を体験できます。
今の自分(心理状態)を
色のイメージで判断できます。
こんな方におすすめ。
部下につい強く怒ってしまう
上司との関係がうまくいかない
お子さんとの関係がうまくいかない
両親とうまくいかない...etc.
普段、人間関係がうまくいかなくて
お悩みの方はこの機会に自分の心を
見える化して、問題解決のヒントを
探しましょう。
申し込み方法
体験会申し込みフォームから
https://ssl.form-mailer.jp/fms/bbb6a118782001
または、こちらの申し込みQRコードから
ご参加お待ちしています。
年齢の差を克服する方法とは パート2
前回のブログでは、
世代の違う相手は、
「理解ではなく認識する」
という内容でした。
メンタルを整えるには
とても時間がかかります。
根気よくトライ&エラーを繰り返し
ゆっくりと進めましょう
さて、今回は
「対話を意識する」です。
皆さん、対話と会話の違いって
ご存じですか?
調べると、
「会話は、二人あるいは少人数で
友好的にお互いに話を進めることで、
たわいのない日常の中でのやりとり
も含まれます」
「対話は、会話のなかのひとつで、
二人がお互いに向かい合って話すことで、
関係性を築くためのコ ミュニケーション
の意味合いが強い」ということです。
ということは、私なりに解釈しますと、
会話は、複数で友好的な情報交換で
日常的な話や雑談。
対話は、1対1で相手の意見や考えを
尊重して、目的に向かって話し合こと
と考えます。
そう考えると、
普段のやり取りが対話をしているようで
会話になっていることの方が多い
のかもしれません。
生きている時代が変われば
価値観や考え方は違うものなので、
より相手の意見や立場を想像しながら
対話を意識する必要があるんです。
前回もお話したように
相手の意見や立場を想像したら
それを理解するのではなく
認識するのです。
認識したことを踏まえて
どう伝えるのか、どう相手に気づきを
感じてもらうのかを考える
ことが重要です。
年齢差で問題を抱えている方は
意識してみてはいかがでしょうか。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここからはお知らせです。
「色彩メンタルトレーニング体験会」
毎月第4水曜日、土曜日に
開催しています。
詳細はチラシ画像でご確認ください。
体験会では、
色彩とコミュニケーション心理学を
融合した「心理テスト」を体験できます。
今の自分(心理状態)を
色のイメージで判断できます。
こんな方におすすめ。
部下につい強く怒ってしまう
上司との関係がうまくいかない
お子さんとの関係がうまくいかない
両親とうまくいかない...etc.
普段、人間関係がうまくいかなくて
お悩みの方はこの機会に自分の心を
見える化して、問題解決のヒントを
探しましょう。
申し込み方法
体験会申し込みフォームから
https://ssl.form-mailer.jp/fms/bbb6a118782001
または、こちらの申し込みQRコードから
ご参加お待ちしています。
年齢の差を克服する方法とは パート1
会社、市民活動、ご近所付き合いなど
様々な場面で年齢の壁ってありますよね。
相手の価値観や行動パターンの違いから
トラブルに発展することも。
この問題はなかなか難しい問題で
ご相談の中でも多いです。
理解しようと努力しても
なかなか理解できず、イライラしたり
関係性が築けず悩んだり、ストレスを
感じてしまいます。
そもそもの話ですが、
理解は不可能です。
考えてもみてください
例えば、
20代の若者は、インターネットが
当たり前に身近で、SNSを使っての
コミュニケーションの方が得意。
50代の私は、そんな便利な道具を
手にしたのはほんの最近の感覚です。
直接に人と話すことでしか
問題解決や情報収集できなかった。
インターネットの話はほんの一例で
世代が変われば色々なことが
違っているものなんです。
それを、さも体験してきたように
理解することは至難の業。
それでも、
世代が違う相手と関わる場面は
避けられません。
その年齢の壁を克服するのには
いくつか方法があります。
①理解ではなく
認識(知る)する
人は理解することで安心感を憶えたり
人との距離が近くなり人間関係も
スムーズにいきます。
だからこそ理解しようと
一生懸命になります。
しかも、この時は感情が優先されるので
理解が出来ればポジティブな感情に、
理解が出来なければネガティブな感情が
出てきてしまいます。
同じ境遇や経験があれば
相手を理解することは
そう難しくはないですが、
世代が違えばそこは難しいです。
だからこそ、
良し悪しを判断するのではなく
ただただ、認識するのです。
「ああ、この人はこんな風に考えるんだ」
「こんな行動をするんだ」
と、知る事だけ。
知らないことを知っていること
にするだけで、余計な感情が
動かず、今の問題に視点が向きます。
しかも、認識はデータとして脳内に
保存しやすいので、認識する量を
増やすことで、想像力が働き
結果的に理解が深まります。
年齢の壁を感じている人は
試してみてください。
ほかにもいくつかあるので
続きは次回。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここからはお知らせです。
「色彩メンタルトレーニング体験会」
毎月第4水曜日、土曜日に
開催しています。
詳細はチラシ画像でご確認ください。
体験会では、
色彩とコミュニケーション心理学を
融合した「心理テスト」を体験できます。
今の自分(心理状態)を
色のイメージで判断できます。
こんな方におすすめ。
部下につい強く怒ってしまう
上司との関係がうまくいかない
お子さんとの関係がうまくいかない
両親とうまくいかない...etc.
普段、人間関係がうまくいかなくて
お悩みの方はこの機会に自分の心を
見える化して、問題解決のヒントを
探しましょう。
申し込み方法
体験会申し込みフォームから
https://ssl.form-mailer.jp/fms/bbb6a118782001
または、こちらの申し込みQRコードから
ご参加お待ちしています。
社内の人間関係がうまくいかない本当の理由とは?
ズバリ!
正しい理解が出来ていないことです。
正しい理解とは?
皆さん、
朝、ご家族と喧嘩したまま
出勤ってことありませんか。
そんな日に限ってトラブルが起きたり
仕事の効率が悪くなったり
いつもはなんてことないことにも
イライラしたり
妙に敏感に反応してしまいませんか。
そんなことが積み重なると
「会社に原因があるんだ」
「特定の人物に原因があるんだ」
などとすり替えが始まります。
それが当たり前になり
いつしかそれが本当のことだと
思い込むようになって
会社の人間関係は最悪になる。
そもそもの要因は、
朝の喧嘩にあるのかもしれません。
つまり、
今起きている現状を
正しく理解出来ていないことが要因。
今起きていることの本当の原因は?
普段と違う反応をしてしまうのはなぜ?
といったような
問いかけが重要になります。
正しい理解が出来ていないと
会社でのストレスはたまる一方
そのはけ口が家庭になり、またその影響が
社内の人間関係を悪化させます
そこで
会社の働きやすい環境を維持するためにも
正しい理解をすることが大切です。
そのためには
目の前で起きたいることに対して
「どんな反応をしているのか」
「その反応は何が原因なのか」
自分自身に問いかけをしてみてください
感情は脇に置いてあくまでも
事実を捉えましょう。
社内の人間関係でお困りの方は
現状と感情の正しい理解をすることが、
社内の人間関係を良好に
保つことに繋がるので
是非考えてみてはいかがでしょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここからはお知らせです。
「色彩メンタルトレーニング体験会」
毎月第4水曜日、土曜日に
開催しています。
詳細はチラシ画像でご確認ください。
体験会では、
色彩とコミュニケーション心理学を
融合した「心理テスト」を体験できます。
今の自分(心理状態)を
色のイメージで判断できます。
こんな方におすすめ。
部下につい強く怒ってしまう
上司との関係がうまくいかない
お子さんとの関係がうまくいかない
両親とうまくいかない...etc.
普段、人間関係がうまくいかなくて
お悩みの方はこの機会に自分の心を
見える化して、問題解決のヒントを
探しましょう。
申し込み方法
体験会申し込みフォームから
https://ssl.form-mailer.jp/fms/bbb6a118782001
または、こちらの申し込みQRコードから
ご参加お待ちしています。
怒りをコントロールする方法
過去の記事で怒りについてお話し
しました。
(まだ読んでない方はこちら)
簡単に振り返ると
怒りは感情で反応から勝手に沸い
てきてしまうので消すことも、
怒らず生きることもほぼ不可能と
いう内容でした。
皆さん、
些細なことだったのに怒りの感情が
抑えられず、大ごとになってしまい
後悔した経験がありませんか?
こ怒りの感情はメリットもあります
が、デメリットの方がはるかに多い
と思います。
だからこそ、
コントロールが必要です。
真っ先にした方がいいのは、
反応をしている体を落ち着かせること。
からだが反応していると思考が停止
状態になります。
怒りの反応を鎮めるには、その場から
離れ深い呼吸を意識しながら深呼吸を
して、反応している体を鎮める必要が
あります。
例えば、
会社で言い争いになったらまず、
その場から離れ呼吸を整えましょう。
そんな時には、私はいつもトイレに
行くようにしています。
誰にも邪魔されずに呼吸を意識でき
る最適な場所は「トイレ」です。
からだの反応が落ち着いたら
何に対してからだが反応したのかを
考えてみましょう。
相手の言葉?
相手の態度?
そもそも相手が関係ある?
自分の機嫌はどうだった?
など、本当の原因は今起きたことな
のか考える必要があります。
なぜなら、怒りの感情は小さい
イライラが蓄積されて、
たまたまその時に溢れてしまうとい
うことが起こるからです。
たまたま小さなイライラの蓄積で、
たまたまその時に溢れてしまって
「八つ当たり」している可能性が
あるかもしれません。
まとめると、
「怒り」は些細なイライラの蓄積さ
れて、そこまで大きい問題ではない
のに限界がきて怒りの感情が溢れて
しまい、大ごとになってしまうので
怒りのコントロールをするには、
そこを抑えておかないといけない
ということになります
いかがでしょう
皆さん、些細なイライラを見逃さずに
その都度、「今私イライラしてるな」
と自分の気持ちを確認することが
怒りのコントロールに繋がります。
怒りを上手にコントロールして
穏やかな一日をお過ごしくださいね。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここからはお知らせです。
「色彩メンタルトレーニング体験会」
毎月第4水曜日、土曜日に
開催しています。
詳細はチラシ画像でご確認ください。
体験会では、
色彩とコミュニケーション心理学を
融合した「心理テスト」を体験できます。
今の自分(心理状態)を
色のイメージで判断できます。
こんな方におすすめ。
部下につい強く怒ってしまう
上司との関係がうまくいかない
お子さんとの関係がうまくいかない
両親とうまくいかない...etc.
普段、人間関係がうまくいかなくて
お悩みの方はこの機会に自分の心を
見える化して、問題解決のヒントを
探しましょう。
申し込み方法
体験会申し込みフォームから
https://ssl.form-mailer.jp/fms/bbb6a118782001
または、こちらの申し込みQRコードから
ご参加お待ちしています。