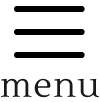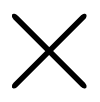ブログ
無自覚な反応が、人間関係をつくっている
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
先週は17年一緒に過ごした
愛猫が旅立ち、次の日には
もらい事故にあうという
落ち着かない日々でしたが
徐々に日常を取り戻しています。
そんなわけで、ブログを
お休みしていましたが
ゆっくりですがブログを再開
していこうと思います。
昨日は週イチクリニックday。
クリニックでは、色グラムを
使って、心のバランスを
見える化し、自分を客観的に
捉えるお手伝いをしています。
今回のワークでの気づきは
「無自覚の反応や行動」でした。
私たちは、日々の反応や行動の
多くを「無意識」で行っています。
そして、そのほとんどに
自覚がないまま過ごしています。
例えば、苦手な人を目の前に
した時の表情。
ほんの一瞬かもしれませんが
嫌な表情は、思っている以上に
相手に伝わっているものです。
その表情が相手に伝わり
警戒心を生んでしまうケースも
決して少なくはありません。
無自覚のうちに発した言葉や
ふとした表情、態度が
思いもよらない誤解や
トラブルに発展することもあります。
しかし、残念なことに
無意識に備わっているものを
すべて自覚することは不可能です。
ましてや、相手と対峙している
その瞬間に気づくのは
とても難しいものです。
だからこそ、普段から
自己理解を深め、自分の
「反応のクセ」を知ることが
大切なのだと思います。
どんな言葉に、どんな反応を
するのか
どんな表情に、心が動き
やすいのか
どんな言葉を選びやすいのか
色グラムのワークでは
そうした無自覚な反応を
事前に見える形にしていきます。
自分の周りでトラブルが
起こりやすいと感じている人ほど
案外、自分の言葉や表情、態度を
振り返る機会が少ないものです。
少しでも多く
自分のクセを知ることが
人間関係のトラブルを
回避するための
ひとつのヒントになるかもしれません。
皆さんは、自分自身の
言葉や表情、態度を
どの程度、自覚していますか。
~~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
サービスのメニュー
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~~
人間関係がこじれる理由は「主観」にある
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
私たちは日々、物事を
「見て」「聞いて」「判断」
しています。
そのとき無意識に使っているのが
「主観」です。
主観とは、事実そのものではなく
自分の価値観や経験を通して捉えた
“解釈”のこと。
同じ出来事でも
人によって受け取り方が違うのは
主観がそれぞれ異なるからです。
とくに企業で働いていると
人間関係の悩みは避けて
通れません。相手の反応が薄い
話しても手応えがない。
その背景には
主観と主観のすれ違いが
隠れていることも少なくありません。
たとえば、上司と部下の関係だと
相手と向き合い言葉を選びながら
話をする時間。
上司は、「成長につなげたい」と
思いあえて語らず考えさせ
ようとします。
一方で部下は「何も言われない
=評価されていない」と感じ
不安を募らせているかもしれません。
同じ沈黙でも
そこに乗せている意味は
大きく異なります。
主観は
その人が生きてきた環境や体験
成功や失敗の積み重ねによって
形づくられます。
自主性を重んじてきた人
(多くを語らず相手に任せる)と
丁寧な関わり(細かく指示を出す)
の中で育ってきた人とでは
「任せる」「支える」の感覚が
違っていて当然です。
だからこそ、相手の考えを
正しい・間違っている
で判断することはとても難しい。
自分にとっての善意が
必ずしも相手の安心につながる
とは限らないのです。
ここで重要なのが
まず自分の主観を客観視すること。
今の受け取りは事実なのか
それとも自分の解釈なのか。
それを会話の前に
一度確認するだけで
対話の質は確実に変わります。
ふとした瞬間に、自分の主観に
気づくことはできていますか?
~~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
サービスのメニュー
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~~
良かれと思って、言いすぎていませんか
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
最近、「質問」という言葉が
耳に残っています。
相手が困っていると、つい答えを
伝えたくなりますよね。
「こうしたらいいですよ」
「それなら、こういう方法
もありますよ」
もちろん、相手のために
言っているんです。
少しでも楽になってほしいし
遠回りしてほしくない。
それって自然なことです。
でも、ちょっと考えてみてください。
良かれと思ってアドバイスしても、
相手の反応が思ったのと違う
ことってありませんか?
「そうじゃなくて…」とか
少し気まずくなったり。
振り返ってみると
あ、これって、相手にとっては
プラスにはなっていない
んじゃないかと気づきました。
答えをもらうと
一瞬は安心します。
でも、その安心は長く続かない。
逆に、自分で考えたことは
時間が経っても心に残るものです。
だから、ちょっと意識して
みませんか。
正解を言う代わりに、
少し質問してみる。
「あなたはどうしたい?」
「どこが一番気になってる?」
「もし失敗しても大丈夫だとしたら?」
すぐに返事が返ってこなくても
いいと思うんです。
その時間も、考えている時間です。
質問を投げかけることは、
突き放すことじゃありません。
「ちょっと考えてみて」
「答えはあなたの心の中にある」
というメッセージでもあるんです。
そして、自分が抱え込みすぎない
ための方法でもあります。
誰かと話すときは
正解を言う前に
少し間を置いて質問してみる。
うまくできなくても
言いそうになった自分に
気づけただけでも十分です。
答えを言わなかった時間も、
質問して考えてもらった時間も、
きっと無駄ではありません。
質問を投げかけることは、
相手を信じること。
そして、自分を少し楽にすること。
もし、相手にアドバイスを
しそうになったらこの話を
思い出してみてください。
~~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
サービスのメニュー
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~~
人間関係が変わる3つの「きく」
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
「きく」をネットで検索すると
3つの漢字の「聞く」「聴く」「訊く」
の違いが飛び込んできます。
私が普段大切にしているのは
「聴く」「訊く」この2つ。
「聴く「を辞書で調べると
「注意して耳に入れる」
「耳を傾ける」
音や話を理解しようとしている
ことがポイントになります。
もうひとつの「訊く」は
「問う」「質問する」という意味。
常用漢字ではないので
一般的には使われてはいませんが
質問を投げかけることが
ポイントになります。
一方で「聞く」は自然と耳に
入ってくる音や言葉という
意味があります。
人間関係で問題を抱えている人の
多くは“聞く”ことを無意識に
していて、お互いに相手のことを
理解しようとする姿勢を
つい忘れてしまっているのかも。
私自身、しゃべることが好きで
ともすると、「聴く」という
姿勢をつい忘れてしまうことも。
だからこそ、「聴く」「訊く」を
意識して相手が何を感じているのか
何を考えているのか、自分の主観
から切り離して、相手の話を
ありのまま情報として受けとめる
ことを大切にしています。
仕事では、その情報を元に仮設
を立て、相手に問いかけ(訊く)
無意識の反応や感覚に自ら
気づいてもらうという方法を
とることが多くあります。
とは言え、気負って上手に聴こう
とする必要はありません。
大切なのは、
すぐに理解しようとしないこと。
すぐに答えを出そうとしないこと。
相手の言葉に一度立ち止まり、
「そうなんだ」と受け取る。
わからなければ、素直に訊いてみる。
聴くこと、訊くことは、
相手を変えるためではなく、
相手を知ろうとする姿勢
そのものなのだと思います。
人間関係でつまづいた時
自分の「きく」を意識して
みてはいかがでしょうか。
~~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
セッション・教室・各種講座
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~~
考える力を引き出す魔法の言葉
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
インターネットが普及し
分からないことは検索すれば
すぐに答えが手に入る
時代になりました。
効率よく正解にたどり着ける
一方で、私たちは「考える時間」
を意識せずに手放している
のかもしれません。
職場や家庭、どんな場面でも
「どうすればいいですか?」
「正解は何ですか?」
と答えを求める声は
少なくありません。
早く答えを出すことは安心に
つながりますが、その答えが
本当に自分に合っているか
どうかは、立ち止まって考え
なければ見えてこないものです。
企業の現場でもよくある光景です。
部下から
「どうしたらいいんですか?」
と聞かれ、つい答えを教えてしまう。
忙しい中で考える時間を待つより
正解を示した方が早いからです。
育成したい気持ちはあっても
成果やスピードを求められる
現実がある。
その結果、部下は動けるように
なりますが、自分で考える機会は
減ります。
管理職は気づかないうちに
育成と効率の間で板挟みに
なっているのです。
だからこそ、明日からできる
小さな行動があります。
すぐに答えを出す前に
一度だけ部下に問いかけてみること。
「あなたはどう思う?」
このひと言が、考える力を引き出す
魔法の言葉になります。
もちろん、突き放すわけではなく
答えを急がず、一緒に考える
という姿勢がとても大切です。
その小さな積み重ねこそが
人を育て、自分も育てる――
まさに、考える力を引き出す
魔法の言葉なのです。
~~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
セッション・教室・各種講座
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~~