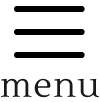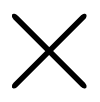ブログ
叱る文化の変化が生んだ世代の壁
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
ここ数年、キャリア教育で
学校に出向き、子ども達と
関わることが増えています。
今の教育の現場や家庭で
昔のように声を荒げて怒る
(叱る)ことが少なくなって
いるのではないでしょうか。
もちろん、大前提として
自身の感情の矛先を子どもに
向けることはあってはならない
と思っています。
ただ、状況によっては「叱る」
ことも必要なことも事実です。
前回の記事でも触れましたが
学生時代に「叱られる」という
経験が少ない子どもたちが
急に「叱られる」という経験を
していかなければなりません。
40代位までの世代は、学校の
先生や両親から、今の時代なら
虐待に近いと思うような
叱られ方をしていたので
叱られ慣れている世代です。
しかし、10代、20代になると
虐待や体罰が問題視され
学校の先生や家庭内でも
「叱る」という行為が悪いこと
のように言われて大声や強い
言葉を受けることが少ない
世代と言えます。
その両者が何の準備がないまま
入社してしまえば業務に追われ
双方の経験の差に目を向ける
余裕すら無くなってしまいます。
何の手立てをしないままでは
双方の溝は深まり、理解する
こともままならない状況に
なってしまいます。
そうならないためにも
お互いのちょうどいい落とし所
を見出せるような研修を
新人だけではなく、社内の
人材にも必要だと思います。
しかも、研修後も実践できる
内容なら研修を土台として
社内の世代が違う人材が
トライ&エラーを繰り返し
ながら、独自の方法をみつけ
出すことも不可能ではありません。
急速に変わりゆく時代だから
こそ、自社にどんな研修が
必要になるか今一度考えて
みてはいかがでしょうか。
~~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
セッション・教室・各種講座
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~~
世代の違いをつなぐ第三者の力
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
昨日、県の取り組みのものづくり
マイスターの出前講座が
地元の高校で行われました。
職人さんと高校生のやり取りで
今、地元企業の中で新入社員と
既存の社員がうまく馴染めない
という問題の要因のひとつが
少しだけ見えた気がしました。
講座の内容は、「小学校に寄贈
するためのベンチを作る」
マイスターの先生から指導
してもらいながら制作。
その、マイスター先生と
生徒のやり取りで、職人さんの
言動に生徒たちが戸惑って
いる場面がちらほら見えました。
今の高校生ともなると
親や学校の先生から大きな声や
怖いと思うような態度で叱られる
経験がほとんどありません。
そんな叱られ慣れていない生徒が
言葉数が少なくて思ったことを
ストレートに言葉にす
ザ・職人さんのような人を
目の前にすると、怒っているわけ
ではなくても、生徒たちは
「怒られた」と思ってしまいます。
今回は、学校という生徒達の
フィールドで、周囲には学校の
先生や私たち外部スタッフが
入っている状況で、しかも
2時間弱の短時間で今日限り
という限定の講座なので
生徒達もなんとか応対が
出来てましたが、これが仕事だと
したら、ちょっと耐えられない
かもしれません。
断っておきますが、職人さん
の言動が悪いということでは
ありません。
不器用だけどめっちゃ優しい
のが職人さんの特徴だと
私は思っています。
でも、経験の少ない子ども達は
そうは受け止められないのが
現実です。
この場合、どちらかが悪いという
ことではなく、お互いの生活環境
の違いが言葉や態度の違いになって
いるのです。
その違いが、双方の思い込みに
繋がりコミュニケーションにズレ
が生まれ、それがうまくいかない
要因のひとつかもしれません。
今回、ちょっと戸惑いを見せた
生徒に「怒ってるわけじゃなく
先生にとってはいつもの口調
なんだよ」と伝えると、生徒は
「なんだ怒ってるんじゃないんだ」
と安心してマイスターの先生と
対話をしていました。
と言ったように、周りにいる
第3者の少しのサポートで
双方のコミュニケーションの
ズレは少しづつ緩和される
のではないでしょうか。
この方法で、すぐさま双方の
関係性が改善できるわけでは
ありませんが、当人同士で
解決するよりははるかに
効果はあると思うんです。
もし、若者との関係性で
お悩みの方は、信頼できる
第3者にサポートをお願い
するのもひとつの方法です。
~~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
セッション・教室・各種講座
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~~
色グラムで紐解くハラスメントの背景と解決のヒント
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
ここ数年、ハラスメントに
関するニュースが話題になる
ことが多くなりましたよね。
世の中では、企業に向けて
ハラスメントに関する講座や
セミナーをたくさん目に
するようになりました。
今の時代は、どの企業でも
コンプライアンスを重視
しているのではないでしょうか。
ただ、ハラスメントを意識
しすぎて、コミュニケーション
がうまく取れなくなっている
ケースも少なくありません。
今回は、ハラスメントに
ついて考えてみました。
ハラスメントについてお話
する前に、私としては
ハラスメントに対しては
あってはならないものだと
思っています。
特に、理不尽なハラスメントは。
ハラスメントとは、簡単に
言えば「いじめや嫌がらせ」に
よって被害者の就業環境を悪化
させる行為のこと。
…と、ハラスメントの話の前に
いつも私がセッションや講座で
使っている「色グラム」に
ついて説明させてください。
この説明がないとこの後の
話がチンプンカンプンに
なっちゃうので。
「色グラム」とは、
心の中に備わっている5つの
特徴を「赤」「ピンク」「黄」
「オレンジ」「緑・青」で表現
して、心のバランスを
折れ線グラフで見える化します。
さて、ここからが本題です。
この「色グラム」の観点から
すると、ハラスメントを
してしまうタイプは
「赤」の数値が高い人。
もしくは、「赤」の特徴を
鎧のように纏っている人。
もちろん、どの色のタイプも
長所と短所が存在していて
ハラスメントをしてしまう人は
「赤」の短所の部分が全面に
出ちゃってるんです。
しかも、「赤」のタイプの人
の多くは「緑・青」の数値が
高い人を選んでハラスメント
行為をする確率が高いんです。
なぜがというと、
「緑・青」の短所でもある
どこかおどおどした態度に
なるところが、「赤」の人に
とっては大好物。
「赤」のタイプの人は
「緑・青」をいじめることで
自分が優位になったように
感じて、脳内では幸せホルモン
でもある「ドーパミン」を
分泌して、「いじめる=幸せ」
という方程式が出来上がります。
「ドーパミン」は中毒性が高い
ので、ことあるごとに
ハラスメント行為をしてしまう
ということになります。
そして、その多くは
「緑・青」タイプの人に
向けられてしまいます。
この場合、多くは「赤」タイプ
の人に要因があるのですが
「緑・青」タイプの人にも
「赤」タイプを引き付けて
しまう特徴があるのも
また事実なんです。
だからこそ、自分がどのタイプ
かを知り、相手との関係性の
パターンをみつけ、双方が
少しずつ改善することで
ハラスメントの問題は少し
改善できると思うんです。
各色の特徴を語ると
とんでもなく長くなって
しまうので、ごく簡単に。
「赤」タイプの人は
大きな声で早口になりやすいので
「緑・青」タイプの人には
ゆっくり、ボリュームを落として
接してみてください。
「緑・青」タイプの人は
恐怖心を消すことはできませんが
「赤」タイプの人は怒っている
わけではなく、大きな声と
話すスピードが速いだけと
自分に言い聞かせてみて。
少し恐怖心が落ち着けば
おどおどした態度が改善できます。
というように、自己理解を
深めれば、建設的な改善策が
見つかりやすくなります。
お互いが少し改善するだけで
ハラスメントの問題は
少しずつ解決に向かうはずです。
~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
セッション・教室・各種講座
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~~
教育の変化を知れば、若手社員との関係性が変わる
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
今の学校教育は、個性を大切に
主体性を持ち自ら行動すること
に重きを置いた探究学習に
力を入れているようです。
この学校教育に関しては
私も肯定的に見ているし
実際、キャリア教育のサポート
で学校に出向くことも
多くなっています。
その時に、毎度感じるのが
私たちが学生の時とは違って
探究学習で外部の大人と関わり
課題や問いを立て、グループや
個人で考え行動する授業が
組み込まれているので、よほど
高度なことをやっている
ということです。
そんな、課題をみつけ考え
行動するなんてことは
私たちが学生の時は
全く体験してませんでした。
そして、その教育は10年程前
から、始まってます。
(もっと前からかもですが)
そんな教育を受けた若者たちが
社会に出てきています。
ましてや、高卒で経験値も
少ない10代の若者たちは
今までの学生生活が抜けない
うちに急に別の世界に飛び込んで
くるようなものです。
例えば、作業ひとつとっても
「これは何のためにやるのか」
「これの意義は」
というようなことが気になる
のが、主体的に考えるという
教育を受けた若者の特徴です。
そんなことを言われたら
私たち世代は「???」と
違和感を感じると思うんです。
経験してきた教育の違いが
今、大きなギャップとなり
様々な問題を巻き起こして
いるのかもしれません。
もちろん、、今の教育の在り方
を否定するつもりは1ミリも
なくて、主体的に考え行動が
できるのはとても素晴らしい
と思ってます。
一方で、自分を抑えて
日々の作業に集中することも
とても重要なポイントです。
若者の価値観や思考
中堅社員の価値観や思考
どちらも大切で必要なこと。
だからこそ、お互いを否定
するのではなく、それぞれの
経験してきた背景を想像して
お互いのいいところを
融合させるような考え方が
必要になってきます。
皆さん、今の学校教育に
触れる機会がありますか。
まずは、今の学校教育に
触れる機会を作ってみては
いかがでしょうか。
~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
セッション・教室・各種講座
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~~~
違いを知り、強みに変える――世代共存の職場づくり
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
この時期になると、新卒で
入社した社員の退職する
という話がちらほらと耳に
入ってきます。
この現象は、今に始まった
ことではなく、昔からある
現象です。
ただ、圧倒的に若者の人口が
減って入社する新卒者が少ない
ということが、大きく
異なっていることでは
ないでしょうか。
今の企業は、人材を確保する
のがとても困難な時代。
一部の企業では新卒者の獲得を
あきらめ、中途採用に舵を切る
という話も耳にします。
しかも、新卒採用をしても
悪ければ、半数の新卒者が
退職してしまうケースも
少なくありません。
また、指導を担う中堅社員も
今の若者のことを理解できず
板挟みで疲弊し、通院を
余儀なくされている方が
増えている傾向でもあります。
この問題は、どちらか一方を
改善すれば解決するという
ことではなく、双方が相手の
ことを知り歩み寄ることが
大切だと思うんです。
例えば、今の教育では
「探求学習」に力を入れ
主体的に考え行動することを
たくさん学んでいます。
一方、40代、50代の人は
先生の言うこと聞くことを
良しとする世代です。
全く違う形の教育を受けて
いれば、考え方や価値観が
大きく違うことは必然です。
時代が変われば、やり方が
変わっていくのは当然ですが
その中でも、受け継がなければ
ならない大切なものもあります。
また、若者の柔軟な発想や
アイデアも今後の会社には
必要不可欠なものです。
お互いの気持ちを想像しながら
双方の「ちょうどいい」ところ
を見つけ出すことが、この問題
の改善する第一歩になる
のではないでしょうか。
そして、お互いのいいところを
引き出し、より働きやすい環境
を作りだすことで、少しづづ
この問題が改善するはずです。
~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
セッション・教室・各種講座
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~~~