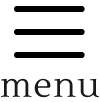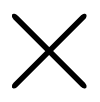ブログ
感情を整える力が、仕事を変える
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
気が付けば、前回の更新から
ほぼ2週間が経ってました。
愛猫の旅たち、叔母の旅立ちが
重なり心の余裕が持てず
ブログを描けずにいました。
やっと落ち着いて、
ブログに向き合えています。
そんな再開のテーマは「感情」。
それでは、本題です。
会社で働いていると、
日々さまざまな感情が動きます。
やる気や達成感、喜びは、
仕事を前に進める力になります。
一方で、怒りや焦り、妬み、
不安も必ず生まれます。
できれば感じたくない感情ですが、
それらもまた、これまでの経験
から自分を守るために
身につけてきた大切な反応です。
ただし、感情にのみ込まれた
ままでは、判断は鈍り、
人間関係も揺らぎます。
キャリアを重ねた今だからこそ
必要なのは、感情を善悪で
裁くことではなく、
「いま何を感じているのか」
を冷静に把握する力です。
そのうえで、感情を抑え込むの
でも、爆発させるのでもなく、
状況に応じて出し方を調整する。
前に出すのか、引くのか。
それは意識して育てていく、
大人の訓練です。
感情は敵ではありません。
扱い方を知れば、
確実に武器になります。
その感情、いまのあなたに
ちょうどいいバランスでしょうか。
~~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
サービスのメニュー
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~~
無自覚な反応が、人間関係をつくっている
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
先週は17年一緒に過ごした
愛猫が旅立ち、次の日には
もらい事故にあうという
落ち着かない日々でしたが
徐々に日常を取り戻しています。
そんなわけで、ブログを
お休みしていましたが
ゆっくりですがブログを再開
していこうと思います。
昨日は週イチクリニックday。
クリニックでは、色グラムを
使って、心のバランスを
見える化し、自分を客観的に
捉えるお手伝いをしています。
今回のワークでの気づきは
「無自覚の反応や行動」でした。
私たちは、日々の反応や行動の
多くを「無意識」で行っています。
そして、そのほとんどに
自覚がないまま過ごしています。
例えば、苦手な人を目の前に
した時の表情。
ほんの一瞬かもしれませんが
嫌な表情は、思っている以上に
相手に伝わっているものです。
その表情が相手に伝わり
警戒心を生んでしまうケースも
決して少なくはありません。
無自覚のうちに発した言葉や
ふとした表情、態度が
思いもよらない誤解や
トラブルに発展することもあります。
しかし、残念なことに
無意識に備わっているものを
すべて自覚することは不可能です。
ましてや、相手と対峙している
その瞬間に気づくのは
とても難しいものです。
だからこそ、普段から
自己理解を深め、自分の
「反応のクセ」を知ることが
大切なのだと思います。
どんな言葉に、どんな反応を
するのか
どんな表情に、心が動き
やすいのか
どんな言葉を選びやすいのか
色グラムのワークでは
そうした無自覚な反応を
事前に見える形にしていきます。
自分の周りでトラブルが
起こりやすいと感じている人ほど
案外、自分の言葉や表情、態度を
振り返る機会が少ないものです。
少しでも多く
自分のクセを知ることが
人間関係のトラブルを
回避するための
ひとつのヒントになるかもしれません。
皆さんは、自分自身の
言葉や表情、態度を
どの程度、自覚していますか。
~~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
サービスのメニュー
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~~
色は気づかないうちに私たちを動かしている
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
色彩メンタルトレーナーなのに
このブログでは色彩について
あまり語っていなかったので
久しぶりに色彩のお話を。
色彩にはそれぞれ意味がある、
というのはご存じでしょうか。
多くの場合、その意味は
私たち一人ひとりが
無意識のうちに持っている
イメージから生まれています。
例えば、
赤は情熱や行動力。
緑は自然、穏やかさ。
ほんの一部ですが、
皆さんが思い浮かべる印象と
大きな違いはないと思います。
そして色彩の効果については、
研究によって明らかにされている
ものもたくさんあります。
色は視覚を通して脳に伝わり、
無意識の反応や感情、
さらには行動にまで
影響を与えているのです。
これは、
私自身の体験からも
強く感じていることです。
以前、交流会に参加した際、
オレンジ色の服を身に着けて
出かけたことがありました。
すると不思議なことに、
こちらから何もしなくても
話しかけられることが
とても多かったのです。
一方で、
黒い服を身に着けて
参加した交流会では、
相手から話しかけられることは
ほとんどなく、自分から声を
かける場面が多くなりました。
どちらが良い、悪い
という話ではありません。
ただ、身に着ける色によって
周囲から受け取られる印象や、
場の中での自分の立ち位置が
自然と変わっていたのだと
感じています。
このように、
日常の中に当たり前に存在する
色彩には、私たちが思っている
以上に意味や効果があります。
その効果を、
自分の足りていない部分を
補うために使うとしたら、
色彩は
「飲まないサプリメント」
のような存在なのかもしれません。
気分を少し上げたいとき。
人との距離を縮めたいとき。
背中を押してほしいとき。
日常にある色彩の力を
上手に取り入れることで、
苦手だと感じていたことも
ほんの少し
やりやすくなるはずです。
~~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
サービスのメニュー
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~~
人間関係がこじれる理由は「主観」にある
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
私たちは日々、物事を
「見て」「聞いて」「判断」
しています。
そのとき無意識に使っているのが
「主観」です。
主観とは、事実そのものではなく
自分の価値観や経験を通して捉えた
“解釈”のこと。
同じ出来事でも
人によって受け取り方が違うのは
主観がそれぞれ異なるからです。
とくに企業で働いていると
人間関係の悩みは避けて
通れません。相手の反応が薄い
話しても手応えがない。
その背景には
主観と主観のすれ違いが
隠れていることも少なくありません。
たとえば、上司と部下の関係だと
相手と向き合い言葉を選びながら
話をする時間。
上司は、「成長につなげたい」と
思いあえて語らず考えさせ
ようとします。
一方で部下は「何も言われない
=評価されていない」と感じ
不安を募らせているかもしれません。
同じ沈黙でも
そこに乗せている意味は
大きく異なります。
主観は
その人が生きてきた環境や体験
成功や失敗の積み重ねによって
形づくられます。
自主性を重んじてきた人
(多くを語らず相手に任せる)と
丁寧な関わり(細かく指示を出す)
の中で育ってきた人とでは
「任せる」「支える」の感覚が
違っていて当然です。
だからこそ、相手の考えを
正しい・間違っている
で判断することはとても難しい。
自分にとっての善意が
必ずしも相手の安心につながる
とは限らないのです。
ここで重要なのが
まず自分の主観を客観視すること。
今の受け取りは事実なのか
それとも自分の解釈なのか。
それを会話の前に
一度確認するだけで
対話の質は確実に変わります。
ふとした瞬間に、自分の主観に
気づくことはできていますか?
~~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
サービスのメニュー
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~~
良かれと思って、言いすぎていませんか
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
最近、「質問」という言葉が
耳に残っています。
相手が困っていると、つい答えを
伝えたくなりますよね。
「こうしたらいいですよ」
「それなら、こういう方法
もありますよ」
もちろん、相手のために
言っているんです。
少しでも楽になってほしいし
遠回りしてほしくない。
それって自然なことです。
でも、ちょっと考えてみてください。
良かれと思ってアドバイスしても、
相手の反応が思ったのと違う
ことってありませんか?
「そうじゃなくて…」とか
少し気まずくなったり。
振り返ってみると
あ、これって、相手にとっては
プラスにはなっていない
んじゃないかと気づきました。
答えをもらうと
一瞬は安心します。
でも、その安心は長く続かない。
逆に、自分で考えたことは
時間が経っても心に残るものです。
だから、ちょっと意識して
みませんか。
正解を言う代わりに、
少し質問してみる。
「あなたはどうしたい?」
「どこが一番気になってる?」
「もし失敗しても大丈夫だとしたら?」
すぐに返事が返ってこなくても
いいと思うんです。
その時間も、考えている時間です。
質問を投げかけることは、
突き放すことじゃありません。
「ちょっと考えてみて」
「答えはあなたの心の中にある」
というメッセージでもあるんです。
そして、自分が抱え込みすぎない
ための方法でもあります。
誰かと話すときは
正解を言う前に
少し間を置いて質問してみる。
うまくできなくても
言いそうになった自分に
気づけただけでも十分です。
答えを言わなかった時間も、
質問して考えてもらった時間も、
きっと無駄ではありません。
質問を投げかけることは、
相手を信じること。
そして、自分を少し楽にすること。
もし、相手にアドバイスを
しそうになったらこの話を
思い出してみてください。
~~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
サービスのメニュー
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~~