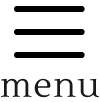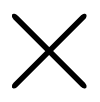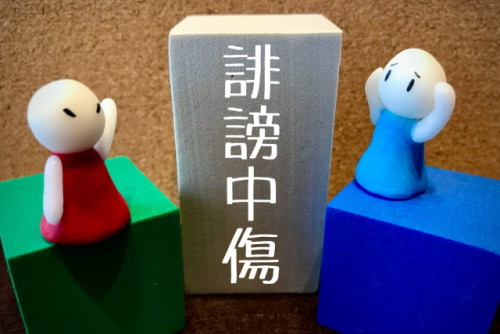ブログ
採用ミスマッチを防ぐ“体験型採用”
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
最近、お仕事…と言っても
職場体験支援コーディネーター
としてのお仕事に携わっていて
経営者の方から「人材確保」が
難しいという声を多く聞きます。
今の採用のシステムだと
履歴書やエントリーシート
に書かれている内容を見て
短時間での面接で採用を決める
と言った方法が主流です。
この方法だと、応募者の
人と成りまで見抜くのは
なかなか難しいものです。
だから、入社後に
「仕事が合わない」
「社内の人と馴染めない」
などの問題が発生して
退職ということになって
しまうことも多くあります。
人材育成には膨大な時間と
コストがかかり、短期間で
退職されてしまえば、それが
水の泡になってしまいます。
もちろん、応募者にとっても
せっかく入社できても
数か月も経たないうちに
身も心もダメージを受けて
ボロボロになるケースも
少なくはありません。
それを防ぐためにも
取り組んで欲しいのは
インターンシップ制度です。
私の暮らしている地域でも
企業と学校を繋ぐ取り組みが
増えてきています。
その取り組みの中にも
インターンシップ制度が
組み込まれています。
インターンシップ制度なら
応募者の人と成りを数日かけて
知ることができます。
そうすれば、入社後に仕事が
合わないだとか、人に馴染めない
という問題はある程度回避できる
のではないでしょうか。
とある経営者は、新卒採用は
せずに、知人の紹介や
「ヘッドハンティングで人材の
確保をしている」と仰っていました。
少子化で若い働き手はどんどん
減少していきます。
だからこそ、効率のいい
人材の確保が大切です。
インターンシップ制度は
理にかなった制度です。
本業のメンタルトレーナーの
視点からも、企業と人材の
マッチングは重要要素で
人間関係のトラブルも少しは
解消できると思っています。
そのためにも、
職場体験支援コーディネーター
の仕事で、サポート出来れば
と思っています。
~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
セッション・教室・各種講座
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~~~
無理に仲良くしなくてもいい、親との関係の整え方
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
この仕事をしていると
人間関係に悩んでいる人の
多くは、家族関係に問題が
あることが多くあります。
特に、両親との関係が
周囲との人間関係に
影響を及ぼすことが
多いように思います。
例えば、大きな声で怒られる
ことや、激しい夫婦喧嘩を
見聞きしていれば、大声で
テンションが高い人は苦手
に感じてしまう可能性が
あります。
と言ったように、両親の
言動が大人になった時に
対人関係に大きく関わって
いるように思います。
だからと言って、あんに
両親との関係を改善する
ということではありません。
たとえ親子と言えど、相性が
合わないこともあります。
交流分析では、先祖代々
受け継がれている
「人生脚本」という刷り込み
のようなものがあって
無意識にその脚本を忠実に
守り暮らしています。
しかも、時代に合わせて
書き換えられた脚本でなければ
時代錯誤の脚本で生きづらさを
感じてしまうものです。
そうなんです、両親も
そのまた両親から渡された
「脚本」を疑うことなく
守ってきたのかもしれません。
自分の両親も、その脚本に
もがき苦しんで生きて来た
可能性もあるということです。
私の場合、高齢の両親に
今更、脚本を書き換えて
もらおうとは思ってなくて
自分の両親が引き継いだ
「脚本」を想像して、今まで
どんな生き方をしてきたのかに
想いを巡らせて、今の言動に
繋がっていると理解しています。
だから、昔に比べたら両親との
関係は良好だと思います。
それでも、両親の言動によって
自分自身の心が乱れたり
傷つくという人もいるでしょう。
そういった場合は無理に
仲良くなろうとは考えず
両親の言動は祖父母から
受け継いだ「脚本」なんだと
思うことで、「しょうかない」
と割り切ることができる
かもしれません。
割り切ることができれば
自分の両親から受け継がれた
「人生脚本」を客観的に見る
ことができて、大切な個所は残し
不必要な個所は消して
自分色の「脚本」に書き換え
られるはずです。
両親とべったり仲良くなる
必要なんてなくて、いい距離感
を保つことで、自分が思う
いい関係になれば
いいんじゃないでしょうか。
お盆休みは、両親が受け継いだ
「人生脚本」を知るいい機会。
どんな子ども時代を過ごして
きたのか聞いてみては
いかがでしょうか。
~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
セッション・教室・各種講座
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~~~
誰かの気分に振り回されないで
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
誰かに傷つく言葉を
投げかけられたとき
「私が悪いのかな」
「何かしたのかも」
と自分を責めてしまうこと
ありませんか?
でも、その傷つく言葉の
理由が「あなたの価値」や
「人間性」の問題ではない
可能性があるということを
心にとめておいて欲しいのです。
誹謗中傷するする人の多くは
心のどこかに「不安」や
「自己否定感」を抱えて
いるものです。
例えば、
・自分は認められてない
・自信が持てない
・不満やストレスが多い
などの心の痛みや不安を
誰かを攻撃することで一時的に
和らげようとする行動なのです。
つまり、あなたを攻撃して
くる人は、あなたを見ている
ようで、実は無意識に自分の
内面と戦っているのです。
かと言って、「なぜ自分なの?」
と思う方もいると思います。
その理由は、あなたの人間性
ではなく、あなたの反応が
その人にとって期待通りの
ものだったからです。
例えば、何か言われるかもと
おどおどしたり、ビクビク
していると、その反応こそが
そういった人たちの大好物
なのです。
少し距離を置いて、よく
観察してみてください。
誹謗中傷する人は、そういう
反応をする人をターゲットに
していることが多いです。
そんな、残念な人に
自分の大切な心や時間を
奪われていると考えたら
どうでしょう、とても
もったいないと思いませんか。
人は、自分の危険をいち早く
察知するために、アンテナを
立てています。
だからこそ、一度嫌な思いを
するとそこに注意を払います。
そうなると、傷つける相手や
言葉、態度がやたらと
気になってしまいます。
そうすると、自分を大切に
思ってくれる人の言葉や
態度に目が向かなくなって
自分の価値が低いと
思い込んでしまいます。
そうならないためにも
自分を傷つける言葉や態度を
浴びたときほど、自分を
大切にしてくれている人の
言葉や態度を思い出したり
実際に会いに行ってみては
いかがでしょうか。
そして、自分を傷つける相手
とは、一定の距離を置くことや
放たれた言葉や態度を
真に受けないようにしましょう。
誰かの気分に振り回されない
ように、自分を大切に想って
くれる人たちとの時間を
大切にしてくださいね。
~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
セッション・教室・各種講座
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~
信頼関係は「心をちょっと開くこと」から始まる
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
今の世の中は、相手のことを
根掘り葉掘り聞くことは
タブーとされています。
ひと昔前は、おせっかいな
おばちゃんやおじさんがいて
嫌でも根掘り葉掘り聞かれて
嫌でも自己開示をする
機会がありました。
それが、今はコンプライアンス
な観点では、根掘り葉掘り
聞くことは良くないこと。
それに関しては、概ね賛成です。
しかし、一方では
自己開示の機会が無くなり
さらに自ら自己開示する
ことは難しくなっている
可能性も否めません。
誰かを信用するには、
ある程度「相手のことを知る」
ことが必要不可欠です。
しかし、今のご時世自ら相手に
根掘り葉掘り聞くことは
なかなかハードルが高いです。
相手がある程度自己開示を
してくれたら、そこはクリア
できる問題だと思います。
この問題は、相手だけでなく
自分自身にも言えること。
誰かに信用して貰いたければ
ある程度の自己開示をする
必要かあるということです。
人によっては、自己開示が
苦手という人もいるでしょう。
でも、何から何まで開示する
ということではないんです。
自分自身を守るためにも
自己理解を進めたうえで
何を話すのか、何を伏せるのか
を判断することが重要です。
確かに、自己開示するには
リスクも伴います。
だからこそ、自分自身で
考え判断するしか方法が
無いのです。
私自身は、自己開示することに
あまり抵抗はありませんが
それでも、伏せている部分も
無いわけではありません。
私の自己開示のポイントは
人となりを知ってもらうために
・体験や経験
・その時の感情
・考えや想い
と言ったことを大切に、言える
範囲を自分で決めています。
気を付けなければならないのは
自己開示=欲求ぶつける
ことではないのです。
そこをはき違えている人も
少なくありません。
自己開示とは、自分が安心できる
コミュニケーションを取るには
欲求ではなく自分自身の情報を
どれだけ相手に渡せるかが
重要になります。
信用されてるか不安を感じたら
自己開示に視点を向けて
大切な情報を渡せているかを
考えてみてはいかがでしょうか
~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
セッション・教室・各種講座
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~
つい悪口…それって心のクセかもしれません
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
皆さん、今までに
友達や同僚と誰かの悪口や
うわさ話で盛り上がった経験
はありませんか。
恥ずかしい話ですが、今思うと
昔の私も、決して褒められる
人間ではなく、誰かの悪口や
うわさ話で盛り上がる側の
人間でした。
その時を振り返りながら
なぜ、人は悪口やうわさ話で
盛り上がるのかを考えて
みようと思います。
今振り返ってみると、
友達や同僚と悪口を言っている
時の私は、ちょっとすっきり
して、気持ちよさすら感じて
いたように思います。
この現象は、いいことではない
はずなのに、脳内では「快」と
感じているから「気持ちよさ」
という報酬を得るというしくみ。
しかも、悪口を繰り返して
いるうちに、悪口=気持ちいい
という構図が脳内にインプット
されてしまいます。
うわさ話もこれと同様で
悪いうわさほど脳内で快楽に
繋がってしまうのでは
ないでしょうか。
だからこそ、悪口やうわさ話
ばかりを口にしている人は
無意識に悪口やうわさ話になる
ネタを探すようになります。
また、同じような脳のクセを
持っている人と一緒にいると
共鳴され、何倍もの快楽に
繋がってしまうかもしれません。
しかも、これも無意識に
同じような脳のクセを持つ人を
引き寄せてしまう可能性も
否めません。
そんな悪口=報酬のクセを
改善するには、感情にフォーカス
するのではなく、事実に目を
向けることが大切です。
例えば、悪口を口にしても
現状は何も変わらないから
この現状を変えるには
どんな行動をすればいいのか
考えを巡らせてみては
いかがでしょうか。
かと言って、つい悪口を口に
してしまうこともあります。
そんな時には、その悪口を
繰り返さないように、また
事実の目を向けるように
意識するようにしています。
悪口やうわさ話からは
何も得るものはありません。
それよりも、自分や相手も
穏やかでいられる方法を
見つけることに目を向けて
みてはいかがでしょうか。
~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
セッション・教室・各種講座
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~