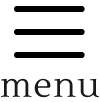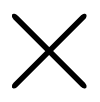ブログ
言葉を変える前に、気づいてほしいこと
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
過去記事で触れたことが
あるかもしれませんが
今回は「言葉」のお話。
人は自分の想いや考えを
表現するのに「言葉」を
使っています。
息をするのと同じくらい
無意識的に使っているのが
「言葉」なんです。
もちろん、考えて言葉を
発するときもありますが、
実は、意識的に発する言葉
よりも、無意識的に使っている
言葉の方がはるかに多いはず。
無意識に選んで口にしている
言葉なので、気が付かない
うちに人との関係に影響して
しまうものです。
言葉のやり取りで、幸福感
を味わえたり、逆に傷つくことや
傷つけてしまうことも
あるのではないでしょうか。
無意識でチョイスしている
言葉なので、思い出そうと
思ってもなかなか難しいのが
現実です。
なので、自分がどんな言葉を
無意識に使っているのかを
知ることが大切になります。
そこでヒントになるのが、
私が使っている
色グラムです。
色グラムは、
人の考え方や感じ方の傾向を
5つの色で表したもの。
この色には、
言葉の選び方のクセも
表れています。
例えば、
赤のタイプ→〇〇するべき
緑・青のタイプ→私なんて
と言った感じ。
言葉に表れるクセは、良い・悪い
ではなくその人らしさ。
だからこそ、
今日意識してほしいのは
たったひとつです。
言葉を直そうとするのではなく、
自分はどんな色のタイプなのか
どんな言葉を使っているのかな
と、立ち止まってみること。
もし、自分の色や言葉のクセを
もう少し知ってみたいと感じたら、
色グラムがそのヒントになります。
気になる方はHPのメニューを
ご覧ください。
~~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
サービスのメニュー
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~~
「自信がない」に振り回されない
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
色彩メンタルトレーニングの
教室をしている中で
よく耳にするのは
「自信がない」という言葉。
このブログで紹介してますが
私の好きな本で
「反応しない練習」の中で
“自信というのは根拠のない妄想”
という一節があります。
これを目にした私は
心のモヤが晴れたかのように
「確かに!」と思わず
声を上げてしまいました。
自信があれば、必ずしも成功
するということはなく
自信がなかったという場合
でも成功することだって
あるものです。
何か新しいことを始める時
この先どうなるかは、誰にも
分からないものです。
しかし、多くの人は
「自信がない」という根拠
のない妄想に囚われ、不安に
苛まれ歩みを止めてしまう
という人も少なくありません。
私自身、その根拠のない妄想に
囚われてしまうこともあります。
そんな時には、この本の
フレーズを思い出します。
自信があるとかないとかより
過去や未来ではなく、今何が
出来ているのか、また出来て
いないのかの事実に目を向け
その事実を受け止める。
そして、今自分が何を
したらいいのかを判断して
行動していくことに
意識をかたむけましょう。
だからといって、不安が
消え去ることはありません。
不安な気持ちになったときに
その気持ちに囚われてしまうか
そうでないかは、自分の心持ち
次第ということです。
不安を抱えている人は
前の自分より、これは出来てると
思えるものを数えてみて。
出来てることに目を向けて
いるといつの間にか
不安は少し小さくなって
いるはずです。
~~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
セッション・教室・各種講座
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~~
未来から考えると、目標は形になっていく
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
皆さん、どんな新年を
迎えましたか?
私は家族と一緒に穏やかな
年の始まりになりました。
そして2日には、
「フューチャーマッピング
書初め」に参加して、今年の
テーマを決めました。
新年を迎えると、多くの人が
今年の目標を考えるのでは
ないでしょうか。
皆さんは、目標を考える時
今の自分の出来ることを元に
目標地点を見上げるように
目標地点を定めていませんか。
数年前までは、私もそういう
ものだと思っていました。
しかし、なかなか目標を達成
することはおろか、目標自体を
忘れているという状況でした。
そんな状況を変えてくれたのが
未来(逆算)思考でした。
未来思考とは、今の自分が
出来る出来ないは関係なく
目標に定めた日時にどうなって
いるかを具体的に想像するんです。
私的には、想像を超えた妄想。
その妄想の中では、
現実ではありえないこともまで
浮かび、「もしそうなったら」と
ニヤニヤしながらワークを
進めていくんです。
すると、今まで目標達成に
程遠い私が、目標を忘れていても
気が付いたら、7割~8割が
達成できてるという不思議。
しっかりしたワークを
やらなくても、目標地点の
自分が、誰といて、どんな
状況で、どんな話をしていて
その時にどんな気持ちなのかを
妄想するんです。
そして、そうなるために
何の努力をしなくてもできる
一歩を考えるんです。
何の努力もいらないことなら
出来そうな気がしませんか。
例えば、今書いているブログを
1年継続しようと目標を立てた
とします、その時の何の努力も
しなくてもできることは
「PCを開く」と言った具合です。
毎年、年明けには目標を立てて
いるのに、なかなか達成まで
到達できないと思っている人は
まずは、今年の年末にどうなって
いるのかを夢想してみてください。
そして、そのために何の努力も
いらない、初めの一歩
babystepを実践してみてください。
今年の年末には、立てた目標が
ある程度達成しているかも
しれません。
皆様、今年も善い年になることを
お祈りしています。
~~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
セッション・教室・各種講座
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~~
年末の大掃除が、心に与えてくれるもの
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
今日から年末年始休暇が
始まった方も多いと思います。
この時期に頭を悩ませるのが
年末の大掃除。
以前、何かのテレビ番組
に出演されていた
整理収納アドバイザーの方が
「お片付けをすると心も安定する」
とお話されていました。
心が疲れていたり、悩んでいる人
の多くは、部屋が散らかって
いるケースがとても多いことを
仕事をしていると実感させられます。
私自身も部屋や特に机の上が
散らかっている時は
頭の中がぐちゃぐちゃになり
悩んでいることが多いです。
部屋の掃除は、幸せホルモンの
ひとつ「セロトニン」の分泌にも
関係していると言われています。
実際、私自身も片付けをした後は
不思議と気持ちが落ち着くことが
少なくありません。
頭や心の中は見えないもの。
だから、日常の些細なところに
投影されているのかもしれません。
本棚や引き出しの一か所だけでも
片付けると、目で見てて成果が
明確に見えるものなので
達成感を味わうことができて
それが幸せホルモンのひとつ
“セロトニン”の分泌に関係して
いるのだと思うのです。
そう考えてみれば
年末の大仕事でもある
“大掃除”は幸せホルモンを得る
絶好の機会でもあります。
冬は日照時間も短くなるので
気持ちが落ち込みやすい季節
とも言われています。
大変な大掃除も少し意識を
変えることで、自分にとって
プラスになる物を受け取れると
思えば、気持ちも少し楽に
なるのではないでしょうか。
どこか一か所でもピカピカに
したら、自分がどんな感情に
なっているか確かめてみてください。
体は疲れているかもしれませんが
気持ちは案外プラスに
動いているかもしれません。
さて、今年のブログ配信は
今日で最後となります。
今年1年、つたない記事を
お読みくださり
ありがとうございました。
来年も、皆様に楽しんで頂ける
記事を配信していこうと
思っておりますので
お読みいただけると嬉しいです。
寒さも本格的になってきました。
くれぐれもご自愛のうえ
善いお年をお迎えください。
~~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
セッション・教室・各種講座
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~~
人間関係が変わる3つの「きく」
おはようございます。
色彩メンタルトレーナーの
織部郁代です。
「きく」をネットで検索すると
3つの漢字の「聞く」「聴く」「訊く」
の違いが飛び込んできます。
私が普段大切にしているのは
「聴く」「訊く」この2つ。
「聴く「を辞書で調べると
「注意して耳に入れる」
「耳を傾ける」
音や話を理解しようとしている
ことがポイントになります。
もうひとつの「訊く」は
「問う」「質問する」という意味。
常用漢字ではないので
一般的には使われてはいませんが
質問を投げかけることが
ポイントになります。
一方で「聞く」は自然と耳に
入ってくる音や言葉という
意味があります。
人間関係で問題を抱えている人の
多くは“聞く”ことを無意識に
していて、お互いに相手のことを
理解しようとする姿勢を
つい忘れてしまっているのかも。
私自身、しゃべることが好きで
ともすると、「聴く」という
姿勢をつい忘れてしまうことも。
だからこそ、「聴く」「訊く」を
意識して相手が何を感じているのか
何を考えているのか、自分の主観
から切り離して、相手の話を
ありのまま情報として受けとめる
ことを大切にしています。
仕事では、その情報を元に仮設
を立て、相手に問いかけ(訊く)
無意識の反応や感覚に自ら
気づいてもらうという方法を
とることが多くあります。
とは言え、気負って上手に聴こう
とする必要はありません。
大切なのは、
すぐに理解しようとしないこと。
すぐに答えを出そうとしないこと。
相手の言葉に一度立ち止まり、
「そうなんだ」と受け取る。
わからなければ、素直に訊いてみる。
聴くこと、訊くことは、
相手を変えるためではなく、
相手を知ろうとする姿勢
そのものなのだと思います。
人間関係でつまづいた時
自分の「きく」を意識して
みてはいかがでしょうか。
~~~~~~~~~~~~~
自分の感情を知るセッションや
教室、講座を提供しています。
ご興味のある方は
このHPの
セッション・教室・各種講座
をご覧ください。
お問合せはこちらから
~~~~~~~~~~~~~