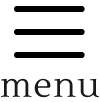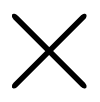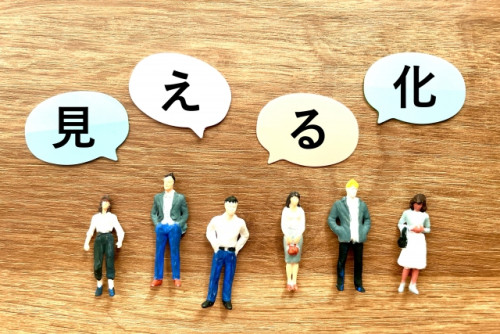ブログ
大人が子供たちに出来ることについて
わたくし事ですが、
つい昨日高校生が企画運営をしている
「UTパレット」の~〇〇の部屋~が
企画をしてくれた「人生ワクワク計画」
全3回講座が無事終了しました。
この講座は、企画した高校生二人と
どんな講座にするか、
どう楽しんでもらうか
参加してくれる人が何を求めているか
考えることから始まりました。
気持ちの部分から、料金の交渉、
講座を企画するために必要なことを
高校生と一緒に考えて実現した企画です。
今回は企画の段階から、
立案した高校生がやりたいこと
企画したことをどう実現するかを
中心に何度かミーティングもしました。
この企画に携わった数か月、
大人の私たちが、子供たちに何が
できるのか、何をしたらいいのか
考えていました。
この企画を終えて今私が感じていることは
このふたりが「これをやりたい」
という心の中から湧き出る「動機」
内発的動機があったからこそ、
企画が成功したのだと思います。
大人でもイベントや講座を企画して
チラシを作り集客をするのは
簡単なことではありません。
それを、このふたりは
学業の傍ら時間を作って、
どんな講座にしたらいいのか
どんなチラシを作ったら
目に留まるのか、一生懸命に考え
やり遂げました。
私自身、今回のように誰かを交えて
企画から考えることは初の試みで
貴重な経験でした。
予想をはるかに超えて
彼女たちは自律的に行動をしてくれていて、
私が何か動かないとと思うことは
何一つありませんでした。
何の心配もなく、
講座の内容だけを考えることが出来たのは、
彼女たちの努力のたまものです。
そんなふたりを見ていて、
大人が子供に出来ることは
環境を整え、子どもたちの内発的動機に
目を向けて、何かを教えるのではなく
困った時や迷った時に、考えるきっかけを
渡す事だけなんだと感じました。
今回関わったのは高校生で
子どもでもなく、大人でもない
ちょうどその中間の世代。
自分の考えで動きたい、
でも不安や心配もある。
そんな世代の彼女たちにとって
今、どんな経験を積み上げるのかが
今後の将来に大きく影響するはず。
自分が考え企画をしたこの経験が
近い将来彼女たちが経験する出来事の
何かヒントになる事を願っています。
時に大人の私たちは、
教えることが役割になってしまいます。
今の世の中は私たち大人が
想像もつかないようなことが
広がる世界が待っています。
その中を生きていく子どもたちに
どんな世の中になったとしても
必要な大切なことは伝え、
何かを教えるのではなく子どもたちの
「やりたい」と思う気持ちに
寄り添うことなんだと思います。
教えたい衝動をぐっとこらえて
何を伝え、どう寄り添い、
困ったときにヒントを渡せるように
自分の知識を磨くことが重要かもしれません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここからはお知らせです。
「色彩メンタルトレーニング体験会」
毎月第4水曜日、土曜日に
開催しています。
詳細はチラシ画像でご確認ください。
体験会では、
色彩とコミュニケーション心理学を
融合した「心理テスト」を体験できます。
今の自分(心理状態)を
色のイメージで判断できます。
こんな方におすすめ。
部下につい強く怒ってしまう
上司との関係がうまくいかない
お子さんとの関係がうまくいかない
両親とうまくいかない...etc.
普段、人間関係がうまくいかなくて
お悩みの方はこの機会に自分の心を
見える化して、問題解決のヒントを
探しましょう。
場合によってお休みになる事もございますので
事前に申し込みして頂くと安心です。
申し込み方法
体験会申し込みフォームから
https://ssl.form-mailer.jp/fms/bbb6a118782001
または、こちらの申し込みQRコードから
ご参加お待ちしています。
多様な人たちと共生するためには
ここ数年、よく耳にするのが「多様性」。
実際、一般企業が障碍者を雇用する
話もちらほら耳にします。
同じ職場に障害のある方や、
精神疾患を患っている方が一緒に
働いていることも少なくありません。
「多様性を受け入れましょう」と
言葉にするだけなら簡単。
実際、目の前にすると、
自分の価値観とあまりにも差が
ありすぎて、困惑します。
思ってる以上に、「多様性」を
受け入れるのは難しいことです。
とは言っても、このまま何もせずに
障害や疾患を持った人との間の
壁をそのまま見過ごしていい
とは思いません。
障害や疾患だけではなく、
人それぞれ価値観や考え方は
違っています。
私が最近になって感じていることは
「受け入れる」のではなく、
どうやって「共生」していくかが
重要だと思います。
障害や疾患と言った枠組みで
考えるのではなく、ひとりひとり
価値観や考え方が違う人間が
どう共生していくのかを
考えることが必要です。
人の数だけ価値観や考え方が
存在するので、正解がある
物ではありません。
相手がどんなクセを持っているのか、
どんな行動をしているのか、
細かく「認識」して、対応をしていく
ことが唯一の方法です。
そして、障害や疾患を
抱えている方も、症状は千差万別ですが
ある程度、治療や訓練で改善する
可能性があります。
「共生」を実現するためには
お互いができることをして
「歩み寄る」気持ちが必要だと
思っています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここからはお知らせです。
「色彩メンタルトレーニング体験会」
毎月第4水曜日、土曜日に
開催しています。
詳細はチラシ画像でご確認ください。
体験会では、
色彩とコミュニケーション心理学を
融合した「心理テスト」を体験できます。
今の自分(心理状態)を
色のイメージで判断できます。
こんな方におすすめ。
部下につい強く怒ってしまう
上司との関係がうまくいかない
お子さんとの関係がうまくいかない
両親とうまくいかない...etc.
普段、人間関係がうまくいかなくて
お悩みの方はこの機会に自分の心を
見える化して、問題解決のヒントを
探しましょう。
申し込み方法
体験会申し込みフォームから
https://ssl.form-mailer.jp/fms/bbb6a118782001
または、こちらの申し込みQRコードから
ご参加お待ちしています。
見得を張ることは悪いことじゃない
皆さん、多かれ少なかれ
「見栄」を張った経験がありませんか?
ここで、ちょっと考えてみてください。
見栄を張りたくなる、もしくは
見栄を張ってしまうのは
どんな状況の時でしょう。
相手にバカにされたくない?
不幸だと思われたくない?
ダメな人と思われたくない?
自分の自信の無さから
つい見栄を張りたくなってしまう
ことが多いのではないでしょうか。
前回の記事の補足ですが、
自己紹介が苦手な人は
この自信の無さが要因で
つい見栄を張ってしまう。
ということは、苦手というより
自己紹介がうまくいってない人
なのかもしれません。
「見栄を張りたくなる」本当の理由とは
「自信の無さ」が大きく関わっていて
言わば自分を守るための「防衛本能」
とも言えるのではないでしょうか。
だとしたら、見栄を張ることは
そんなに悪いことでしょうか。
ありもしない嘘の見栄の張り方
は良くないかもしれませんが、
少し努力をしたら出来そうな
見栄だとしたらどうでしょう。
結果論かもしれませんが、
見栄を張ってとしても、
その見栄の通りの状況になっていれば
見栄も本当に切り替わります。
実は私も時には見栄を張ります。
ちょっと自信はないけど、
少し頑張れば出来そうなことは
「できます」と見栄を張ることで
「やるしかない」状況を作ります。
「できます」と言った手前
「出来ませんでした」というわけ
にはいかないので、「やるしかない」と
いう気持ちで取り組みます。
この場合は、見栄ではなく
見得を使った方が正しいかも。
「見栄」と「見得」の違いを説明すると、
見栄は、周りの目を気にして
自分をよく見せようとすること
見得は、自信ありげに
大げさな言動をすることです。
ということは、
全くの嘘でなければ、
「見得を張る」という解釈も
出来ると思うのです。
見得を張ることは、時には
自信が持てない自分の背中を
自分自身で押すひとつの方法
なのかもしれません。
今の講師業を始めるきっかけも、
お声がけくださった方に
「できますよ」と見得を張った
のが始まりでした。
ということで、見得を張ることは
時には自分を新しい世界へ
進ませてくれる力があると思います。
やってみたいけど勇気が出ない時に
「できます」と大見得を切って
自分の背中を押して
新しい世界の扉を開きましょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここからはお知らせです。
「色彩メンタルトレーニング体験会」
毎月第4水曜日、土曜日に
開催しています。
詳細はチラシ画像でご確認ください。
体験会では、
色彩とコミュニケーション心理学を
融合した「心理テスト」を体験できます。
今の自分(心理状態)を
色のイメージで判断できます。
こんな方におすすめ。
部下につい強く怒ってしまう
上司との関係がうまくいかない
お子さんとの関係がうまくいかない
両親とうまくいかない...etc.
普段、人間関係がうまくいかなくて
お悩みの方はこの機会に自分の心を
見える化して、問題解決のヒントを
探しましょう。
申し込み方法
体験会申し込みフォームから
https://ssl.form-mailer.jp/fms/bbb6a118782001
または、こちらの申し込みQRコードから
ご参加お待ちしています。
人は案外自分のことが理解できていない
突然ですが、
プライベートの集まりに参加したとして
30秒で自己紹介をしてください。
どうでしょう、
すんなり自己紹介できますか?
自己紹介をすんなりできる人は
そう多くはないと思います。
私の周囲でも「自己紹介が苦手」
という人がたくさんいます。
なぜ多くの人が自己紹介を
苦手だと思うのでしょうか。
その理由は、大きく分けると
2つあると思います。
①自分の事がよく分からない
②見栄を張りたくなってしまう
自己紹介を例にあげましたが、
この2つが生きていくうえで
大きなポイントとなるところです。
少し前置きが長くなってしまいましたが、
今回のお話は、
「案外自分のことって分からない」
というお話です。
過去記事でもお話しましたが、
人は97%が無意識で行動しています。
自分でも気が付いていない
行動や考えのクセがあるのです。
この「クセ」は日常の生活では
見えていないのが現状です。
だからこそ、時間を作って
クセの見える化が必要になります。
クセを客観的に捉えるためには
自分に質問を投げかけることが
必要になります。
例えば、
今日目にした物、口にした物、
かけられた言葉などが、
好きなのか、嫌いなのか
心地いいのか、不快なのか。
ほんの少し自分のためだけの
時間を作って自問自答を繰り返し、
出来れば、自問自答した内容を
メモしておいてください。
そして、少し日数を開けて
その日に、目にした物、口にした物
かけられた言葉などを自問自答
してみてください。
何回か繰り返すうちに
自分のクセが見えてきます。
自分の行動や考えのクセを知ることで
トラブルの軽減や、ストレスの軽減に
繋がってきます。
冒頭で例に出した
「自己紹介」にも役に立つので
一度試してみてください。
②の「見栄を張りたくなってしまう」
のお話はまた次回に。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここからはお知らせです。
「色彩メンタルトレーニング体験会」
毎月第4水曜日、土曜日に
開催しています。
詳細はチラシ画像でご確認ください。
体験会では、
色彩とコミュニケーション心理学を
融合した「心理テスト」を体験できます。
今の自分(心理状態)を
色のイメージで判断できます。
こんな方におすすめ。
部下につい強く怒ってしまう
上司との関係がうまくいかない
お子さんとの関係がうまくいかない
両親とうまくいかない...etc.
普段、人間関係がうまくいかなくて
お悩みの方はこの機会に自分の心を
見える化して、問題解決のヒントを
探しましょう。
申し込み方法
体験会申し込みフォームから
https://ssl.form-mailer.jp/fms/bbb6a118782001
または、こちらの申し込みQRコードから
ご参加お待ちしています。
お盆のこの時期に考えること
お盆休みはいかがお過ごしですか?
8月は、ご先祖様をお迎えしたり
広島・長崎原爆投下の日や
終戦記念日など、
考えさせられる時期です。
個人的にはこの時期に
第二次世界大戦をテーマにした
映画やドキュメンタリーを
観ることにしています。
私の両親は、戦時中に生まれて
戦争の記憶がうっすら残る年代ですが
終戦が幼少期だったため
語ってくれるのは、戦後の復興の
話がほとんどです。
復興の時代の話も様々な苦労と
葛藤が入り混じったとても
重要な話ですが、戦時中の話も
私たち戦争を知らない世代は
知らなければならないことだと思います。
そして、祖父母や若くして旅立った兄の
ことを思い出して家族で話題にする
きっかけとなる時期です。
戦時中、お国のためと戦い
この世を去らなければならなかった
多くの人たち、そして未来ある若者たち
がどんな思いで散っていったのか。
はたまた、若くして旅立った兄や
幼馴染のことを思い出すことで
私が今生かされているのは
何のためなのか、残された私は
これからどんな人生を送るのか。
日常の生活の中では、
そんなにじっくり考えることは
そう多くはないので、
1年のうちのこの時期は、
あえて考えさせられるようなものを
観たり聞いたりするのかもしれません。
はっきり答えが出るわけではなく、
毎年、仕事をセーブしているこの時期に
色々なものを観たり、聞いたりして
自分のこれからをじっくり考える
いい機会だと思っています。
そして、この時期に
両親の昔話を聴き、
どんな人生を送ってきたのかを
知ることで、ひとりの人間なんだと
しみじみ実感するというわけです。
皆さんも、このお盆の時期に
ご先祖様や自分の両親の
若かりし頃に思いをはせてみては
いかがでしょうか。
今回は、とりとめのないお話でしたが、
最後までお読みくださり
ありがとうございます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここからはお知らせです。
「色彩メンタルトレーニング体験会」
毎月第4水曜日、土曜日に
開催しています。
詳細はチラシ画像でご確認ください。
体験会では、
色彩とコミュニケーション心理学を
融合した「心理テスト」を体験できます。
今の自分(心理状態)を
色のイメージで判断できます。
こんな方におすすめ。
部下につい強く怒ってしまう
上司との関係がうまくいかない
お子さんとの関係がうまくいかない
両親とうまくいかない...etc.
普段、人間関係がうまくいかなくて
お悩みの方はこの機会に自分の心を
見える化して、問題解決のヒントを
探しましょう。
申し込み方法
体験会申し込みフォームから
https://ssl.form-mailer.jp/fms/bbb6a118782001
または、こちらの申し込みQRコードから
ご参加お待ちしています。