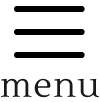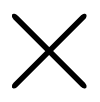ブログ
人との関係性を築くには「探求心」が必要
最近、地域の学校に探求の授業の
お手伝いに行くことが増えています。
「探求」何かを探し求めることで
よく探求心という言葉なら
よく耳にしますよね。
学校でも、私たちのような
地域で働く大人たちや
様々なツールを使って「探求」を
深める授業を進めています。
そのひとつで、
OODA(ウーダ)ループという
意思決定プロセスに準じて
「探求学習」を進めている
学校もあります。
その探求学習をお手伝いしていて
気づいたことがあるんです。
人との関係性を築き続けていくことは
まさに「探求学習」と同じ。
先程の「OODA(ウーダ)ループ」は
観察(observe)
方向づけ・仮説構築(orient)
選択(decide)
行動(act)
を繰り返すプロセスです。
このプロセスを人との関係性に
置き換えてみると
観察➩道具(言葉、表情)選び
➩接し方を決める➩話すといった
感じになると思うんです。
前回の記事でも、
人との関係性を築くのは
とても面倒で時間がかかるもの
しかも、生きる上での悩みの
ほとんどが人間関係です。
その面倒で時間がかかって
悩みのほどんどを占めている
人との関わりを築いていくのには
ひと工夫が必要です。
そのひと工夫に
先程の「OODA(ウーダ)」の
プロセスを繰り返してみるのも
効果が高いと考えます。
人との関係性を築くには
これという正解やマニュアルは
存在しません。
まさに「探求」なんです。
もし、人との関係性に悩んでいる
のなら、悩むことをやめて
探求なんだと捉えることが
改善の第1歩になる
のではないでしょうか。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここからはお知らせです。
先月からお話していた
新講座や新メニュー
それに伴う料金変更など
大幅なリニューアルが完了しました。
メニューをご覧になりたい方は
こちら⇦をクリック。
講座の詳細については
お問合せフォームにて
ご連絡ください。
第1期生の募集は年内を考えています。
こちらは詳細が決まり次第
お知らせします。
「話が通じない」と感じたときの対処法
ほとんどの人が、人と関わる中で
考えていることや、思いが伝わらない
という経験があるはずです。
そんな時は、もどかしさや苛立ちを
感じてしまいますよね。
知り合い程度の関係なら、距離を置く
ことも可能ですが、関係性が深い
場合はそう簡単ではありません。
特に、社内での人との関わりの場合
年齢も違えば、育った環境も違う
人々が集まり会社や組織の方針に従って
労働をするという環境です。
しかも、多様性を受け入れることに
舵を切り始めた世の中ですので
もっと自分との違いを感じる
ことも多いのではないでしょうか。
人はそれぞれ価値観や考え方が
違う生き物で「違う」ことを
前提に考えなければ
人との関わりは難しくなります。
例えば、同じ組織で働いていれば
「普通はこうするだろう」と
組織内での常識が存在します。
この状況になると「違う」という
認識をするのが難しくなってしまいます。
この「違い」に目を向けなければ
相手に何か伝えようと思っても
なかなか伝わらなくなってしまいます。
「この人話が通じない」と感じた時
実は、この「違い」に目が向かず
「こうするのが常識」
「普通はこう考える」など
違いを受け入れることが阻害されて
いる可能性が高いと言えます。
お互いに「違い」を受け入れ
相手をじっくり観察して
何を考え、どんな言葉を頻繁に
使っているのか、どんな言葉や態度に
反応を示すのかを知ることが
いちばんの近道です。
「話が通じない」と相手に怒りを
ぶつけても一歩も進みません。
かえって職場の雰囲気も悪化して
他のトラブルを引き起こす要因にも
なりかねません。
そもそも、人との関係性を築くのは
とても時間がかかり面倒なことです。
面倒だからと言って細かいことを
疎かにしてしまえば、関係性を築く
ことは到底難しいです。
特に会社組織の中では
相手を理解することよりも
相手を認知することの方が
重要になります。
理解は相手を自分のことのように
感じ相手と同じ感覚になる事で
認知とは、事実のみを受け取る
言わば情報収集に近いものです。
理解をしようと思っても
数年はかかります。
まずは、情報収集に意識を傾け
認知を深めることで
伝えたいことが伝わる方法を
見つけ出すことが先決です。
認知を深めることが
職場の雰囲気を改善することに
つながり、伝えたいことが
伝わりやすい状況を生み出す
ことになります。
「話が通じない」と
感じる時には相手を知ること
から始めてみてはいかがでしょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここからはお知らせです。
先月からお話していた
新講座や新メニュー
それに伴う料金変更など
大幅なリニューアルが完了しました。
メニューをご覧になりたい方は
こちら⇦をクリック。
講座の詳細については
お問合せフォームにて
ご連絡ください。
第1期生の募集は年内を考えています。
こちらは詳細が決まり次第
お知らせします。
人との関係を築くことは面倒だけど必要なこと
「人は鏡」という言葉を
耳にしたことがありませんか?
人は自分を映しだす鏡だと
思っている人の方が多いと思います。
それも間違いではないんですが
自分のことを確認するために
相手が必要になっているとも
言われています。
もっと言うと、
人は自分の課題を映し出して
くれる大事な存在ともいえます。
だからこそ、生きていくうえで
人との関係性を断つこと
不可能で、関わることを
避けることは難しいのです。
また、誰しもが承認欲求を
持っています。
この承認欲求を満たすという
面でも、人との関わりは
切り離せません。
ということで、どんなに面倒だと
思ったとしても、人との関わりを
持たずに生活することは
とうてい無理な話というわけです。
人との関わりを避けられない
としたら、自分も相手も幸せになる
やり方を見つけた方が賢明です。
では、なぜ人との関係は
面倒だと感じるのでしょう。
それは、価値観や考え方が
「違う」ということが
いちばんの理由です。
自分と全く同じ価値観や考え
だったら楽かもしれませんが、
長い時間を一緒に過ごす家族でさえ
同じ価値観や考え方でいるのは
とても難しいことです。
だからこそ、人は他人と
分かり合うために言葉や表情、
仕草など様々な道具を使って
コミュニケーションを図ります。
自分がどんな道具で他の人と
コミュニケーションを
取っているのか、相手がどんな
道具を使って人と
コミュニケーションを取っている
のかを知ることが先決です。
その「違い」を認識することが
人との関係性を築くのに
重要なポイントになるはずです。
そして、相手に対して
自分の価値観や考えに
賛同してくれることを
過剰に期待をしていないか
振り返ってみてください。
その期待を持っていると
賛同してもらえない時の
ダメージはかなり強く
苛立ちや憤りを感じてしまいます。
なので、過剰に期待することは
やめて、自分も相手もOKという
立場になるようにトライ&エラーを
繰り返すことが必要です。
その立場を維持できれば
人との関係に振り回されることも
少なくなるはずです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここからはお知らせです。
先月からお話していた
新講座や新メニュー
それに伴う料金変更など
大幅なリニューアルが完了しました。
メニューをご覧になりたい方は
こちら⇦をクリック。
講座の詳細については
お問合せフォームにて
ご連絡ください。
第1期生の募集は年内を考えています。
こちらは詳細が決まり次第
お知らせします。
仕事での内発的動機はどう動かす?
前回の記事では、
心の底から湧き上がる「やりたい」
と思う気持ち、内発的動機が大切
というお話でした。
今回は、「仕事での内発的動機」
について考えてみました。
この「内発的動機」というものは
持ちやすい職業(業務内容)と
持ちにくい職業があると思うんです。
例えば、
私たちのような自営業者、サービス業
については、顧客から直接反応が
受け取ることが出来る職業なので、
内発的動機に結びつきやすい。
製造業のように、自分の目の前にある
製品の完成系も定かではない部品を
作っているような場合は、
内発的動機に結びつけるのは困難。
製造業でも開発に携わる部署は
話は別で、自分が開発に携わっていれば
製品に対する価値が明確で
「いいものを作りたい」といった
動機に繋がるかもしれません。
といったように、
内発的動機は職業や職種によって
持ちやすさと持ちにくさが
分かれてしまいます。
1日8時間働くとすると
人生の3分の1は働いています。
働き続けるためにも内発的動機が
重要になると思うんです。
内発的動機が持ちにくい
製造業などの職種の場合の
内発的動機を持つ(持たせる)には
どうしたらいいのでしょう。
会社全体でのビジョンだけでは
社員一人一人の内発的動機には
なかなか繋がりにくいのが現状です。
例えば、部署ごともっと言えば同じ
プロジェクトを担っている
仲間の間で、目指す方向や
クオリティーなどを共有する。
仲間で一つの目標達成を
目指すことで内発的動機に
働きかけることが可能になる
のではないでしょうか。
もちろん、自分が携わる製品の
クオリティーなどを追及することや
隣で働く仲間のためになど、
人それぞれに内発的動機に繋がる
要素は周りにたくさんあるはずです。
内発的動機が動くことで
長い時間を費やす働くということが
もっと充実感を味わえる時間に
なるのではないでしょうか。
また、リーダーの立場で働いている人
にとっては、チームの士気を
あげるためにも、個々の内発的動機を
動かす材料がどの位あるのか
見直してみるのもいいかもしれません。
さて、皆さん
本当にやりたいと思うことを
出来ていますか?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここからはお知らせです。
先月からお話していた
新講座や新メニュー
それに伴う料金変更など
大幅なリニューアルが完了しました。
メニューをご覧になりたい方は
こちら⇦をクリック。
講座の詳細については
お問合せフォームにて
ご連絡ください。
第1期生の募集は年内を考えています。
こちらは詳細が決まり次第
お知らせします。
内発的動機が行動し続ける原動力
誰しもが、仕事や趣味に関わらず、
一度は「これをやりたい」と
時間が経つのを忘れて何かに没頭した
経験があるのではないでしょうか。
しかし、年を重ねるほど
この「やりたい」という気持ちが
環境や立場によって、心の奥底へ
押し込められてしまいます。
しかも、この現象が中高生の中でも
「浮いてしまったら」
「周りにどうみられる」
など、周りの目を気にして
素直に出せないことが多くなっています。
だからこそ、やる気にならなかったり
やらされている感覚から抜け出せない
状況になってししまいます。
私自身もこういった経験があって、
20年ほど前にカフェを経営していた
時がまさにそんな感じでした。
カフェをやりたいと思ったきっかけは
生前兄が言っていた一言で
「車屋の隣で喫茶店やったら?」
兄が果たせなかった夢を
代わりに私がという気持ちと
何か特別なことをしなければ
自分の存在意義がないと
思い込んでいたんだと思います。
開業したての頃は、楽しさや
達成感に似た感情で何とか
やり過ごしていました。
数か月後には、辛さの方が上回る
ようになり、1年も経たず限界を
感じ店を閉じることにしました。
今思えば、趣味での料理は好きでしたが
自分が食べたいと思うからであって
誰かのために料理をすることは
好きではなかったと気づいたんです。
これって、かなり致命的ですよね~
思い出しても笑っちゃうくらいです。
このエピソードは、
私の心の底から湧き出す
「内発的動機」がなかったから
大変なことでも楽しむことが
出来なかったのだと思います。
といったように、「内発的動機」
心の底から「やりたい」という
気持ちがとっても重要になるのです。
この「内発的動機」は、
車に例えるとまさにガソリンです。
ガソリンを入れなければ車が動かない
と同様に、「内発的動機」がなければ
行動し続けることが出来ないのです。
今は、何をするにしても
このことをいちばん重要視しています。
それがないと、大変なことでも
楽しむことが難しくなって
続かないのだと思っています。
今、皆さんは心の底から
「やりたい」と思うことはありますか?
仕事?趣味?
何でもいいから「やりたい」と思う
気持ちに素直なってみてください。
ただ、この「内発的動機」は
仕事になると難しい面も
あるかもしれません。
これ以上は長くなってしまうので
続きはまた次回お話します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここからはお知らせです。
先月からお話していた
新講座や新メニュー
それに伴う料金変更など
大幅なリニューアルが完了しました。
メニューをご覧になりたい方は
こちら⇦をクリック。
講座の詳細については
お問合せフォームにて
ご連絡ください。
第1期生の募集は年内を考えています。
こちらは詳細が決まり次第
お知らせします。